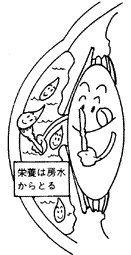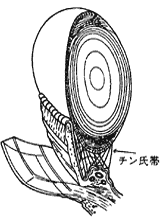|
ひとみは瞳孔といわれます。虹彩の中央にあるまるいあなで,光の入口です。これはカメラでいえばシポリにあたるところで,光が強い(明るい)と小さく縮み,夜や暗いところでは大きくなって目の中に入る光の量を加減します。また,それと同時に,近くを見るときは縮小して像をはっきりとさせます。 ひとみの特徴としては, (1)角膜の後ろ2〜3mmのところにあります。 (2)虹彩は色素をもっていて光の入るのを防ぎます。 (3)虹彩は毛様体という組織で固定されています。 (4)ひとみは,興奮したり感動したりすると大きくなり,睡眠中は強く縮小しています。 |