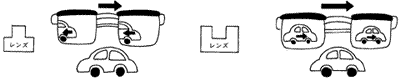|
|
(1)レンズの種類 1)単焦点レンズ 遠用だけ,近用だけといったようなメガネに使います。 (2)機能 1)常用無色レンズ・・・光の透過率が90%以上もある無色のレンズで日常かけるメガネに使用されます。 |
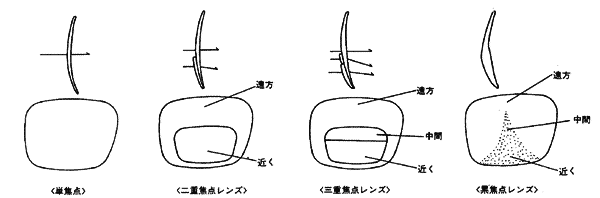
メガネは13世紀の中ごろイタリア人によって発明されたといわれていますが,当時はすべて老眼鏡として使われていました。15〜16世紀ごろから,貴族や僧職者の間に広く使われるようになりましたが,とても高価なものでした。日本では,徳川家康と足利義政のメガネが保存されています。
|
メガネは使い方によって次のように分けられます。 ・視力矯正用 一 近視,遠視,乱視,老視の矯正 ・保 護 用 一 有害光線(紫外線,赤外線)を避ける ・美 容 用 一 ファッションのため ・スポーツ用 一 スキーのゴーグル,水中メガネなど ・ドライブ用 一 昼間か夜間使用の目的をはっきりして使います。 |
|
|
(1)レンズの種類 1)単焦点レンズ 遠用だけ,近用だけといったようなメガネに使います。 (2)機能 1)常用無色レンズ・・・光の透過率が90%以上もある無色のレンズで日常かけるメガネに使用されます。 |
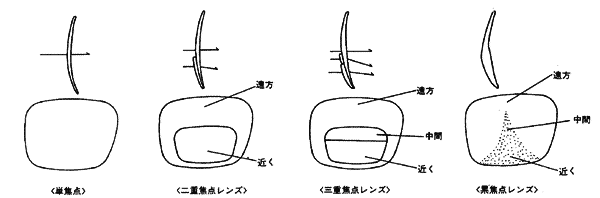
|
(1)メガネをはずすとき 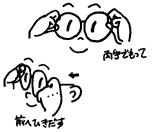 (2)メガネをふくとき 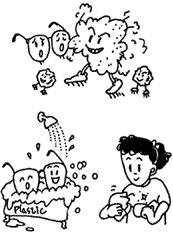 |
メガネの正しい取りあつかい方。 (1)メガネのかけ・はずしは両手でする。 メガネは,鼻,こめかみ,耳の三点でバランスよく支えているもので,このかけ方,はずし方を片手で行なうと,左右が不均等になって,かけごこちが悪くなります。また,つる(テンプル)が開きすぎて,ズレ落ちやすくなったり,左右均等でなくなりバランスがくずれてきます。メガネのはずし方は,両手でつるの元の部分を持ちあげ,まっすぐ前の方へ引き出すようにします。 (2)メガネをふくときは, ・砂やホコリ,金属の粉末が付着したままふかないこと。 ・ふくものは専用のレンズふきか,ガーゼ,さらし木綿のようなやわらかいものでふくこと。 ・プラスチックレンズは,ふく回数をへらし,うすい中性洗剤で振り洗いをして水ですすぎ十分乾燥させるか,または,やわらかい清潔なペーパーなどで軽くよごれをふき落とすこと。 (3)レンズを下向きに置かない。 レンズは球面になっているので,レンズの中心に傷がつきます。 (4)高温・多湿のところへは置かないこと。 レンズ,フレームが変形・変質することがあります。 |
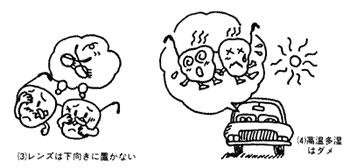
|
メガネはかけている間に,つるの部分や鼻パットの部分が変形し,左右のバランスがくずれ,鼻や耳が痛くなることがあります。そのため,なるべく正しい使い方になれることです。 |
||
|
|
||
|
子ども用のメガネについて (1)子どもははげしい運動をよくするため,安全性を考えてプラスチックレンズを使う必要があります。 (2)メガネが鼻からずっている子どもには鼻パットの部分をよく調整し,フィッティングにいつも注意しましょう。 (3)子どもたちの鼻幅は,おとなにくらべて狭いために,どうしてもずれやすくなりがちです。レンズの中心を目の高さに正しくもってくるためには,必ず子ども用のフレームを使用することが大切です。 |

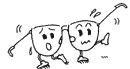 |
おとなと子どもでは顔の大きさ,目の幅が異なり,フレームのサイズや鼻の幅,つるの長さなどが違います。そのため,レンズの大きさ,重量などが違い,どうしてもおとなの方が重くなります。最近では強化金属の枠やプラスチックレンズにより昔は50gもあったメガネが20g程度と非常に軽くなってきています。 |
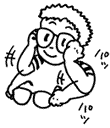 |
近視のメガネについては,かけはずしをするから悪くなるということはありません。映画を見る,黒板を見る,車の運転をするなど,必要なときにかければよいでしょう。また,近視の度の弱い人は,本を読んだり,字を書いたりするのに不便がなければ,メガネをかけなくてもよいでしょう。もし近くのものを見るときも見にくければ,メガネをかけて見ればよいわけです。 しかし,遠視や乱視のメガネの場合は,治療の意味もあるので,常にかけていなければなりません。 一般的に述べれば以上のようになりますが,年齢や職業など個人によって違ってきますから,メガネを処方されたら,必ず眼科医にたずねておくことが大切です。 |
|
|
|
||
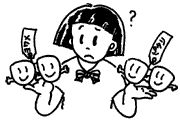 |
よくいわれることですが,ひとつの考えとしてはあたっているかもしれません。というのは,近視の場合で,メガネをその人の近視の度ピッタリに合わせると(完全矯正という),近くのものを見るときにかなりな調節が必要となってくるため,多少矯正をひかえめにしてメガネを処方することが多いからです。しかし,これも個人差のあることですから一様にはいえません。ところが,遠視の場合は反対で,同じように見える度のうちのいちばん強い度を処方します。これも,そのほうが無理な調節を必要とせず,目の負担が少なくてすむからです。したがって,必ずしもメガネの度は弱いほうがよいとは限らないわけです。 |
|
|
|
||
|
これについては,医学的根拠はありません。おそらく,メガネをかけている人がはずしたとき,急にぼやけて見えるので,裸眼視力がメガネをかけていなかった頃より低下した,近視の度が進んだ,と錯覚するのだと思います。しかし,自分に合っていないメガネをかけ続けるのは,目に過度の負担をかけ,近視の進行の原因のひとつになることもあるかもしれません。メガネをかけている人は,定期的に検査をしてもらうことが大切です。特に,高校生以下では,半年に一度くらいの検査は必要でしょう。 |
||
|
|
||
|
|
メガネが合わないと起こる症状は, (1)メガネをかけたときは見えていても,ずっとかけ続けているとだんだん見えにくくなってくる。 (2)頭痛,肩こり,頭が重い,吐き気がする。 (3)イライラなどのストレスが起こる。 (4)眼精疲労が起こる。 (5)目だけでなく,体の健康を害することもある。 そのため,メガネができあがっても,もう一度眼科医で検眼して,そのメガネが合っているかどうか調べてもらうことが大切です。 |
 3.吐き気
3.吐き気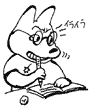 4.イライラ
4.イライラ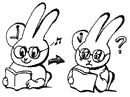 5.眼精疲労
5.眼精疲労
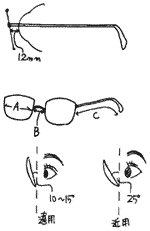 |
メガネのレンズと目の角膜の_損点の距離は,一般に12mmが正しいといわれています。この距離から遠ざかると,凹レンズでは実際の度数より弱くなり,凸レンズでは強くなります。老人がメガネを少しずらして近くの新聞を見ている人がいるでしょう。おそらく,老眼鏡の凸レンズの度が自分には弱いので,目からレンズを離して,実際の度より強くして見ているのだと思います。
|
||
|
|
|||
|
視力表にある赤と緑の一字か二重丸を見てもらい,どちらの色の方が明るく,はっきりと見えるかを検査して,今かけているレンズの度数が合っているかを調べます。これは,赤の波長の方が長く,緑の波長の方が短いという赤と緑の光の波長を利用したものです。近視では,緑は網膜の手前に焦点を結ぶためぼやけ,赤は網膜付近で焦点を結ぶのではっきりします。また,遠視ではその逆となります。 ・赤,緑がはっきり見える・・・使用しているメガネの度数は正しい ・赤がはっきり見える・・・近視矯正の凹レンズが弱い ・・・遠視矯正の凸レンズが強い ・緑がはっきり見える・・・近視矯正の凹レンズが強い |
|||
|
|
|||
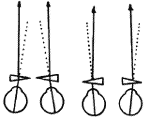 |
主として斜視の治療などに使うメガネです。 一つの物を両眼で見ようとするとき片方の目がそちらに向いていても,他方の目は内や外に向いていたりして,一つの物を両眼同時に見ることができません。そこで,メガネにプリズムを入れて,光を屈折させ,両眼で同じ方向が見られるようにするためのメガネです。 |
||
|
|
|||
|
メガネを動かすと,レンズを通して見る物体は,凸レンズでは逆,凹レンズでは動かすと同じ方向に移動します。 |