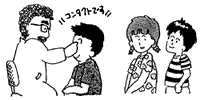日本では約1600万人がコンタクトレンズを使っているといわれています(平成17年度)。また約6000〜6500万人がメガネを使用(常用あるいは老眼鏡などを必要時に使用)しているとされています。
(1)コンタクトレンズの利点
1)目とともに動くため,プリズム作用・収差がない。
2)他人に装用していることがわからない。
3)度が強くても,メガネのように大きさが実物と違って見えることがない。
4)乱視が強くてもメガネより視力がでやすいことが多い。
5)メガネの視野は約120度(フレームがじゃまをするため),コンタクトレンズの視野は杓200度もある。
6)気温,湿度の変化にも,レンズがくもりにくい。
(2)コンタクトレンズの欠点
1)ごみが入ると痛い。
2)面倒である。
3)長時間使用できない。
4)定期検査を受けなければならない。
いずれにしても,コンタクトレンズは,一日中使用できるわけではなく,朝や夜間などのコンタクトレンズの装脱着前後はメガネを使うことになりますし,旅行やドライブには,紛失やケガのため,必ずメガネを持っていった方がよいでしょう。また,どうしても,コンタクトレンズに慣れることのできない人もいます。
 異物感が無く装用感が良い
異物感が無く装用感が良い
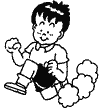 激しい運動にも落ちにくい
激しい運動にも落ちにくい レンズの下にごみが入りにくい
レンズの下にごみが入りにくい
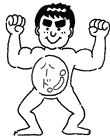 レンズの光学性が良い(角膜不正乱視がある人でも視力がでやすい)
レンズの光学性が良い(角膜不正乱視がある人でも視力がでやすい) こわれにくい
こわれにくい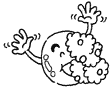
 細菌やカビに汚染されにくい
細菌やカビに汚染されにくい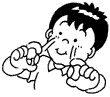

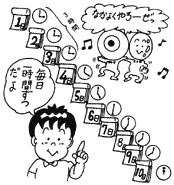
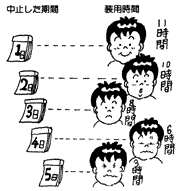
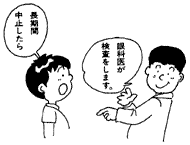












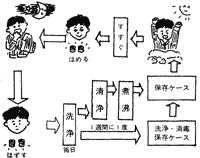

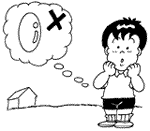
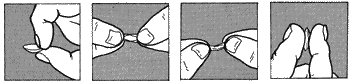
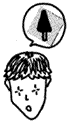
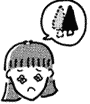

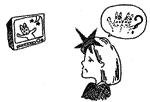
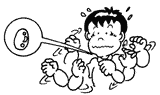

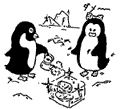


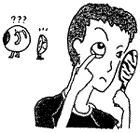
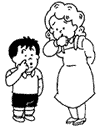
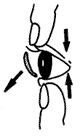 ハードレンズの場合
ハードレンズの場合
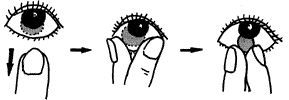 ソフトレンズの場合
ソフトレンズの場合